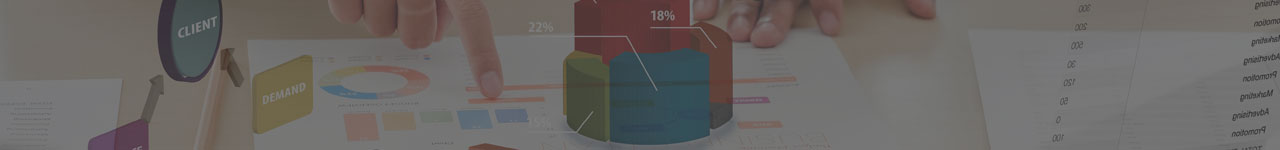概要

●初めての著書
市販の書籍で初めて出版したのが『旅行業』(図3)という共著本です。東洋経済新報社から1986(昭和61)年に出版されました。それまで小論文はたくさん書いていましたが、本を出したのは初めてでした。
本が出版されたのは、観光労連の委員長から受けた相談がきっかけです。「組合の委員長で国内旅行出身者は海外のことがわからないし、海外旅行出身者は国内のことがわからない。委員長であれば、旅行業の全体像がわかなくてはいけない、そのようなテキストを作ってくれ」と言われました。

図3『旅行業』(1986)
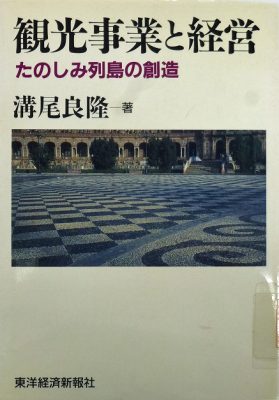
図4『観光事業と経営』(1990)
そこでJTB、近畿日本ツーリスト、日本旅行、東急観光から4人を集め、旅行業は基本的に中小企業ということで、中小企業に精通している経済評論家杉岡碩夫先生に委員長をお願いしました。私は事務局長を務め、1年くらいかけて報告書をまとめました。すると杉岡さんが「すごくいいレポートだ」と言って、東洋経済新報社に出版するよう売り込んで、『旅行業』が完成したのです。
その縁で、その後1990(平成2)年に東洋経済新報社から『観光事業と経営』(図4)という初めての単著本を出しました。1994(平成6)年には、財団で『観光読本』(図5)を出版していますが、その前に、1986年に『観光ビジネスの手引き』(図6)を私が主査をしていた旅行調査室のメンバーで東洋経済から出しているのです。
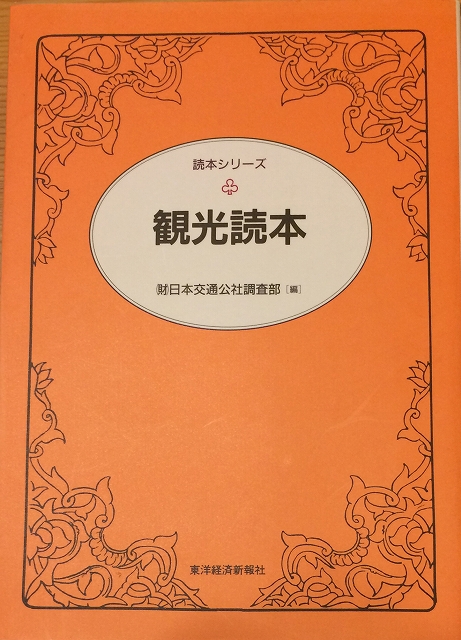

図6『観光ビジネスの手引き』(1986)
●博士論文の執筆
1970(昭和45)年に鈴木忠義先生の提案で、財団の自主研究で観光資源を客観的に評価する研究が始まりました。研究期間は2年間で、事務方の中心となった私は研究成果を『観光地の評価手法』(図7)としてまとめ、多方面から注目を集めました。
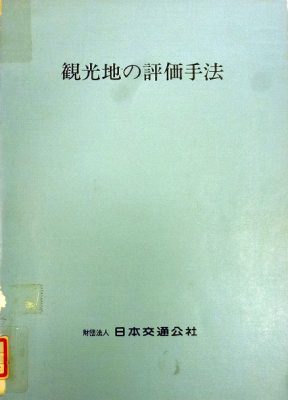
図7『観光地の評価手法』(1970)
しかし、やり残した課題も多かったので、財団に「もう2年継続できないか」と希望を出したのですが、ダメだと却下されました。そこで、10万円の自主研究費をもらって、やり残した課題を『湖の評価手法』で研究をしました。
ちょうどその頃、日本交通公社の出版事業局も観光資源の研究に注目するようになりました。『新日本ガイド』(写真2)というガイドブックを発刊することになり、全国の観光対象資源や施設を評価しようということで、私を指名して依頼が来ました。
そこで私は観光地の評価手法のメンバーに協力を依頼し、以前の研究手法を改善して、より具体的な尺度でより多くの観光資源を対象に評価を行いました。こうして新日本ガイドは1973(昭和48)年から発行がスタートしました。私は1975(昭和50)年に、この研究をまとめて『多次元解析による観光資源の評価』という論文を発表しました。

写真2 『新日本ガイド』
するとその論文を見て、教育大時代からご指導いただいている筑波大の山本正三先生から「これまでの研究をもっと発展させると、博士論文になる」という電話がかかってきました。先生は私が「先行研究として、この研究がなぜ必要かという論文を新しく1つ書きなさい。それに今回発表した論文を合わせて3本揃えば博士論文に仕上げることができる」と言われました。
私は自分の研究がオリジナルだと思っているから、先行研究なんて全然読んでなくて、文献を探したり読んだりするのが大変でしたが、後輩達がいろいろ本を持っていたので、アメリカやイギリスの論文を随分読みました。その結果、自分の研究にはオリジナリティがあると改めて確信でき、自信が持てました。
財団の仕事が忙しかったので、論文を書くのは土日や夏休みなどで、月に1度は論文を持って筑波大まで通いました。山本先生は具体的な指摘はしないのですが、「週刊誌のような文章だ」といったコメントを言われ、それを受けて書き直すことを繰り返しました。当時はパソコンがないので、ちょっとした文章の切り貼りも大変でした。
とても感謝しているのは、副査となった奥野隆史先生が私の論文を懇切丁寧に「てにをは」まで細かく全部直してくれたことです。その影響で、私が大学で学生を教えるようになった時も、卒業論文は全部目を通して、一字一句まで直すようにしています。
●立教大学への転出
私は1983(昭和58)年から隔年で立正大学の地理学科、1985(昭和60)年からは立教大学の観光学科で非常勤講師を務めていました。博士論文を仕上げて、1985年に筑波大学で博士号をとると、大学の地理教員にならないかという誘いが2つくらいありました。でもまだ組織が弱体の財団を辞めたら勝手すぎると思って断りました。
その後、調査部長に生え抜きの原さんがなったし、直採用で入った林さんや小久保君などが課長になったので、これでいつ辞めてもいいかなと思っていたら、1988(昭和63)年の10月頃、私が北海道に出張していた時に、立教大学から誘いの電話がかかってきました。教員が一人急に辞めることになったので、専任として採用したいというお話でした。
私は「わかりました。行きます」と答えました。そして財団に戻り、原さんと東京教育大学の先輩でもある総務部長小澤博さんの2人だけに、私の意向を伝えました。小沢さんは行きなさいといってくれましたが、「若い人が動揺するといけないので、2月までは絶対に言わないでくれ」と頼まれました。
翌年2月になり、課長を全部集めて、私は財団を辞めると伝えました。やはりみな動揺しましたが、こうして財団を離れ、1989(平成元)年4月から立教大学社会学部観光学科の教授に着任しました。
当時の立教大学の観光学科は財団のレポート等を参考にして勉強しているような状況でした。そこで、着任してすぐ行ったのがカリキュラムの見直しです。観光英語など、専門学校で教えるような実務的な科目を廃止し、観光計画などの専門科目を増やそうと主張しました。その理由として挙げたのが「将来、日本のいろんな大学に観光学科や観光学部がたくさんできるだろう。その時に参考にするのが立教大学のカリキュラムだから、今から恥ずかしくないものを作っておきたい」ということでした。
観光計画なんて難しくて学生が理解できないと言われたけど、それは教える人の問題だと言って…。結局、私の希望はかなりカリキュラムに生かされました。財団時代から非常勤で10年くらい通っていたので、周囲も私が生意気なことはすでに知っていたし(笑)。ちょうど私が着任した年にリゾート法が施行されたので、観光に対する機運の高まりもありました。
立教大学で観光学部を作るときも「全国各地に観光学科がどんどんできている。そういう中で、抜きん出るために、立教大学は観光学部を一番手で作らないとだめだ」、「二番手、三番手ではダメだ」と力説しました。
学部長会で観光学部が必要かどうか、かなり議論が行われました。文学部や法学部の連中は「観光学部を作ってもいいけど、観光が学問と言えるのか」と言う。「法学部や文学部は明治時代にできて歴史はあるけど、外国の借り物ではないか」と反論し、「これから新しいものを作るのだから、時間がかかる。産みの苦しみを理解してくれ」と主張して戦いました。そうして奮闘した末に観光学部が生まれたわけですが、作ってよかったと今でも思います。
大学へ入ったとき決意したのは、「学生が観光業界に就職するときに、溝尾ゼミです、と胸を張っていえるようなゼミを作ること」でした。授業もしっかりと教えるが、大人数なので、ゼミこそが学生を鍛える場と考えました。学生には、「縁故、地縁、贈収賄なんでもよいが、自分より優秀なひとを推薦しろ」、面接は、ゼミが2年からだったので、希望者が1年のときに3年生2名、2年生1名が一つのグループになって面接させ、最大20名まで合格にしました。一方、レポートも提出させ、こちらは、私が採点し、面接で落ちた学生で優秀なのを拾い上げました。ゼミでは、学生が新聞を読まないので、アナログは承知で新聞を読ませ、テーマ別の発表をさせました。学生の中には、初めて日経新聞をとり、その面白さがわかり、卒業しても日経新聞をとるようになったというのもいます。年に4~5回の東京や東京周辺の日帰りフィールドワークで、地域の見方を教え、年に1回、3泊のゼミ調査を、東京を離れて国内外で行いました。それらはすべて報告書として残っています。大学では必修ではありませんが、私のゼミではもちろん、全員卒業論文を書かなければいけません。卒論の構想や発表を、2年~4年、全員が新治村に毎年集まり、ときには卒業生も集まり、議論しました。こうして300名以上のゼミ生が誕生し、旅行業や行政の中堅となって活躍しています。
私は2007(平成19)年、立教大学を65歳で定年退職しましたが、在籍18年間で社会学部の観光学科長を6年、移行期もあったので重複して観光学部観光学科長を4年間務め、観光学部の二代目観光学部長を務めました。当時、観光学科から博士号が一つも出ていなくて、韓国の大学から「立教大学はなぜ博士号をださないのか」といわれました。「必ず出す」と約束して、韓国出身の私の教え子が観光分野での博士第一号となりました。彼はいま九州産業大学の学部長を務めています。その後、たくさんの博士が誕生しています。
この研究・事業の分類
| 関連する研究・事業 | |
|---|---|
| 関連するレポート | |
| 発注者 | 公益財団法人日本交通公社 |
| 実施年度 | 2015年度 |