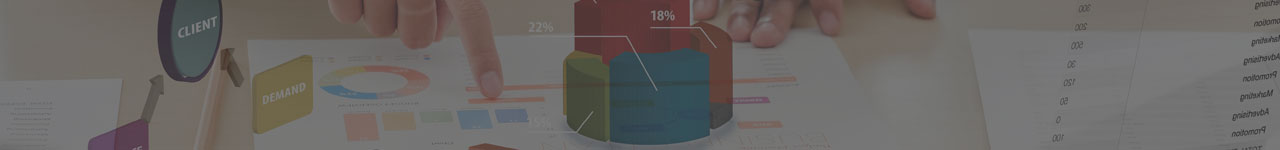概要

(1)これからのわが国の観光、観光地づくりに必要なことは何か
●自由時間(活動)と長期休暇の制度化
万国共通、どこの国の人間にも共通するキーワードは、時間です。僕は人間と観光を考える原点の一つに「自分の時間(自由時間)に自分のお金で自分の好きなことをする」ことを主張してきました。
自由時間は働く人達にとって、休暇休日ですが、この中で特に長期休暇をきちんと制度化することが急務です。取得の仕方は一週間を単位に、いろいろあって良いのです。連続休暇の中で、ゆっくり、ていねいに自分の好きなこと見つけ出し、試行錯誤しながら自分の時間の使い方を実践し、喜び、楽しみを体験することが必要なのです。勿論、夏の首都圏を考えれば、避暑、暑中休暇は必然です。ハッピーマンデーなど供給サイドに立った諸施策を国が率先してやっていることは方向が違っていると思います。世界の中で、国民の祝日が毎年変わる国など聞いたことがありません。
フランスでは1930年代にバカンス法ができて、自分の自由時間をどう使うかという話の中から受け皿としてのリゾートが開発・整備されてきましたが、日本の場合はいきなり首都圏に対して地方の振興という受け皿の話から入ってしまいました。これが我が国のリゾート問題の最大の課題です。
リゾート法に基づくリゾート開発の議論が盛んだった頃、我々はリゾート開発研究会を立ち上げ、事務局も担当しました。「開発したリゾートに誰が行くのですか。あなた方自身が行かなかったら、需要も市場もありませんよ」と切り出すと、「私は忙しくて行けません」という担当者が多かったことを思い出します。
僕は常に生活者は賢い消費者にならなければ・・・、供給者・事業者は、良質な消費者を育てるという発想と実践を・・・と言ってきました。長期休暇は働く人の権利で「この時間をどう使うか」は基本的に個々人の問題ではありますが、ある種の消費者訓練は必要です。その気にならないと良質な消費者も育たないわけです。
東京五輪についても、「おもてなし」とか「ホスピタリティ」など産業サイドの受け皿の話ばかりしていないで、皆さん自身が、自分達自身が観光客になってごらんなさい、国内は勿論、海外旅行をどんどんしてみたら・・・と言いたいわけです。
そういう体験を重ねれば、「(観光客としては)こういうことをされたら嬉しい」「こういうことは嫌だ」と自然に考えることができて、わざわざ「おもてなし」などと言わなくても自然に受け入れ、交流が生まれるはずです。産業サイドの論理だけではなく、もっと根本的な観光と人間の関係、消費者と観光の関わりといった視点が必要ではないでしょうか。
●五感を体験できる観光地づくり ―「時速4kmの世界」をどう再構築するか―
僕の観光開発計画者としての長年の課題は、日本の温泉地や観光地をもう少し美しくチャーミングなところにしたいということに尽きます。
例えば、「道の駅」を評価する専門家は少なくありませんが、僕はどうも疑問です。大事なことは集落―農村集落や観光集落(地)を再生させることだと考えているからです。道路沿いに道の駅という名のドライブイン的単体施設を整備することは、順序が逆だと思います。モデルの一つ、ドイツのロマンチック街道には道の駅はありません。都市から小さな町や集落まで街道沿いに駐車場とトイレと案内板があり、そこからちょっと歩くと都市や集落に出会えます。ブラブラ歩くと雑貨店や飲食店があったり、たまたま地元のお祭りに出会えたりといった楽しみがあります。
僕が口を酸っぱくして言ってきたのが「時速4kmの世界」です。ヒューマンスケールとも言い換えられますが、車に煩わされずに歩く速度(時速4㎞)、実際はもっとゆっくり、のんびり、ぶらぶらと様々な空間を楽しむこと。車に乗っているだけでは味わえない楽しみ、五感を最大限に発揮して感じられる発見や喜びが観光の基本だと思っています。
1971年に発行された岩波新書『自動車の社会的費用』は東大経済学部の宇沢弘文教授が書かれた本ですが、自動車社会について問題提起した名著であり、今でも観光に関わる人だけでなく地域や都市づくりに関わる方々の必読本だと思います。
自動車(産業)がこの国の産業や生活に与えた影響は計り知れないものがありますが、反面、そこのけそこのけ自動車が通る、ということで路地裏がなくなったり、公共交通機関が衰退したりといろいろマイナス面が多々ありましたが、最も大きな問題は集落の崩壊です。
都市部はそれにいち早く気づき、道路局や都市局のお金で失われたものの回復に力を注ぎました。住宅団地を整備する際には歩行者空間をきちんと分けてヒューマンスケールの空間を取り戻したり、中心市街地の活性化では自動車を制約して歩いて行くことが足りる空間づくりが積極的に行われました。温泉地に代表される観光地はどうでしょうか。ほとんどそうした対応ができていないと言えます。
見直すべきは、個人的にも社会的にも車とどう付き合うかです。時速40㎞の世界から時速4㎞の世界へいかに導くか。車で訪れた来訪者を車から開放して、快適な空間を歩く速度で楽しんでもらうにはどうしたらいいか。そのキーワードは、車がなくとも生活できるコミュニティや集落の再生だと思います。
集落・コミュニティの魅力といっても、大都市と20万都市、あるいは小さな町や村ではそれぞれ違うと思います。逆に違うから魅力的なのです。都市・都会といなか(田舎)―観光地を含めた農山漁村の違いは、一言で言えば、生活や産業などの変化のスピードの違い、自然に近い速度でゆっくり変わる世界と急激に変化する都市・都会。イギリスの湖水地方の佇まい―暮らし方、生き方とナショナルトラスト(運動)から学びました。コンビニと雑貨店の違いと言ってもよい。住民が育てるわがまちの様々な中小零細な製造・小売業の育成がポイントだと思います。
車社会の到来によって魅力が失われてしまった集落も少なくありません。集落をもう一度ヒューマンスケールで生活でき、来訪者にも楽しめる場所に取り戻せるかどうかが、日本が美しく魅力ある国土に再生できるかどうかのポイントだと思っています。
●「住んでよし訪れてよし」と「住めば都」
観光まちづくりが言われるようになったのは2000年、21世紀に入ってからだと思いますが、それ以前はまちづくり、観光地づくりでした。観光まちづくりの一環で、亡くなられた木村尚三郎先生が観光政策審議会の中で発言されたフレーズ「住んでよし訪れてよし」もこの時期盛んに使われました。僕はこの二つのフレーズには疑問を抱いています。「住みにくいけど、訪れてみたい」ところはたくさんありますし、それが観光地らしい観光地だとさえ思っているからです。観光まちづくりも伝えたい概念、中身がもう一つよく理解できません。
もう一つ「住めば都」というフレーズがありますが、これはその通りだと思います。納得できます。何かと不便なところだけど住んでみると意外にいいところ、住み心地は悪くないというところは、たくさんあります。そういう人がたくさんいますと言った方が正しいかもしれません。リゾート都市を目指すべき軽井沢あるいは別府や熱海など国際観光文化温泉都市の目標の一つは間違いなく「住んでよし訪れてよし」である必要がありますが、沖縄の竹富島や北海道の阿寒湖温泉など国立公園の中にある観光地は、この目標はあてはまらない、否当てはめてはいけないと考えています。
このテーマは観光地づくりの主体論の議論とつながります。「観光地づくりの主体は住民だ」という専門家は結構数多くいます。僕は「解っちゃいねーなぁ・・・」と小さな声で言いつつ、観光地づくりの主体は観光者・観光客であると申し上げています。観光で訪れた来訪者を満足させることが観光地づくりの目標であり、そのために住民が多少不便になることもあり得ると考えています。鈴木先生にかつて、「便利にすることが開発ではない」と教えていただきました。観光地づくりというのはそういうものだ、と言いたいのです。
「まちづくり」は、住民のために何をどうして住み易いまちにするかの「解」を求めることであり、「観光地づくり」は観光者のために、「観光まちづくり」は観光(事業)でまちづくりがどこまで万能かを作業することだとそれぞれ使い分けています。
日観協の機関誌「観光」も流行に沿って「観光まちづくり」になり、最近「観光とまちづくり」になりました。編集者の意図は聞いておりませんが、僕流に言うと間に「と」を入れたことによって、解り易くなりました。
温泉観光地について言えば、大型バスが観光の主流となり、大型旅館の玄関まで入ってくることが当たり前になりました。温泉街まで車が入ってきて、歩行者より車優先になってしまいました。歩行者優先のまちづくりの社会実験まではするのですが、なかなかその先に行くのが難しい状況です。
結局は観光客よりも自分達の便利さを優先していると思われても仕方がないのでは・・・。そこで「住んでよし訪れてよし」が目標と言い出すと、ますます矛盾してしまうと思います。スイスの有名な山岳リゾート、ツェルマットの観光地づくりをもう一度繙く必要があるかもしれません。
●後ろを向いて前へ歩め ―歴史に学ぶ―
僕は現状認識の重要性を言う時、必ず言っていることは「100年を振り返って(トレースして)、10年先を展望し、現実の諸課題に対応しては・・・」と。
今、観光業界や宿泊業界だけではなく、産業・企業で人手不足が問題になっているようですが、高度経済成長期昭和40〜50年代にも同じような問題がありました。若い人がどんどん都市・都会に出て行って、地域の旅館を含めて地元の中小零細企業は人手不足が問題になっていたのです。
当時、横溝さん達と箱根の旅館組合から依頼され現状調査に取り組みました。人手不足と言われる経営者に、「ではあなたの旅館では、どの部門で何人足りないのですか」と質問して、明確に回答できた経営者はほとんどいませんでした。ですから、今、人手が足りないと嘆いている旅館経営者には、まず自分のお父さんやおじいさんに聞いてごらんなさい、同じ経験してきたはずですからと言いたいです。
社員がいなければ経営はできませんから、必然的に規模を小さくせざるを得ません。ある意味で当たり前のことです。北陸の温泉観光地とも長いつきあいがあります。A、Bという2つの旅館がありました。経営者は同世代で、A旅館は時流に乗ってどんどん客室を増やして大型化し、ある時期は成功したかにみえましたが、その後、手に負えなくなって他人の手に渡ってしまいました。B旅館はいくつか理由はありましたが、客室数を減らし、中身を充実させ自分の手のうちにはまる経営を志し、今も存続しています。
A旅館が躓いた原因は、過剰な設備投資もありますが、やはり経営トップの問題、社員や組織運営問題があったと思います。人手が足りないのは、人が集まらないのは、働く場所としての魅力がないという認識の上に立たないといけないのではないでしょうか。最終的には一人一人の経営者と経営手法の問題だと思います。止まって考えることも必要なんじゃないかなと思います。
鴨川グランドホテルが山口県の西長門に新しいホテルを開業した時、高卒の社員を集めるために当時としては飛び抜けた社員寮を建設し、保護者や入社予定者に寮や職場の内覧会を行いました。画期的な試みで、後日社員寮を視察した旅館経営者が「うちの旅館の部屋より立派だ」と(笑)。
もう一つ。那須ビューホテルの箭内さんは、業界の関係者なら伊良湖ビューホテルの開業とレストランシアターで知らない人はいない経営者のお一人でしたが、旅館も大学卒業生を採用できる職場にしなければ、そのためには、どうしても東京に事業所が必要だという経営戦略に基づいて誕生したのが、浅草ビューホテルです。
この例のように、人材、新卒を確保しようと努力する経営者、実現している事業家はいつの時代にも必ずいます。ただ、「人手が足りない」と声高に言っているだけでなく、きちんと取り組みをしているところをしっかり拾い上げることも必要で、きちんと評価をして的確にアドバイスすることもコンサルタントの役目の一つだと思います。
●「コンサルタント=町医者」の果たすべき役割
地域の自治体が人口減少に直面し、限界集落を抱えて模索し続ける状況は、古くて新しい問題です。農山村ばかりではなく観光地にもたくさんあります。僕は人間が住んでいる町も生き物だとすれば、町や村にも「ご臨終」という現象があるのでは・・・と思います。その時どうするか。延命措置をとるのか、安楽死、自然死・・・どうするか。
勿論、これは難しい問題で当然いろいろな意見があります。「たった一人でも生活者が住んでいれば、その村や町はバックアップすべきだ」という専門家もいます。
反発や反論を承知で敢えて申し上げれば、限界集落になる前に、場合によっては、ご臨終の宣言をし、延命措置(公共投資)はしない方がいいのではと考えています。ことは人間一人一人の生き様、人権の問題にもかかわることですから、軽々しく言えないにしても、人口減少に歯止めがきかず、高齢化が進む集落の人たちに対しては、ある程度の人口が集積する集落や町に移転・移住を促し、そこで車がなくても生活ができる選択肢を積極的に提示・提案すべきではないかと思っています。集落の自治力、集落を包含する自治体の自治体力とも関連して、判断する必要はありますが・・・。合併も対等より吸収合併の方が、効果的な場合が少なくないと思います。ケース・バイ・ケース、個別解で、丁寧に対応すべきだと思います。
テレビや新聞は、一組、二組の移住をセンセーショナルに伝えて、再生の切り札のように持ち上げるケースがありますが、そう単純ではないはずです。過去にも失敗をしている例があるわけです。例えば、ペンションブームのように、脱サラした家族の都会から海浜や高原など田舎への移住が、一時盛んに行われましたが、教育や医療の問題、後継者など、結局、長続きせず廃墟になったところが少なくありません。
そういう意味で、地域にアドバイスする立場のコンサルタントは、過去50年、70年の間にどういうことがあったかをきちんとトレースし、その蓄積の上に立ってアドバイスすることが必要です。
注射を打ったり、薬を飲ませたり、対処療法によってとにかく町や村を活性化させること、延命させるのがいい仕事をしていると錯覚するのは間違いであり、必要な時に言うべきことを言うのが町医者としてのコンサルタントの役割の一つではないでしょうか。
今は、観光に関してもいろいろな省庁から国の予算が出ています。「この町は将来どうあるべきか」というビジョンがないままに、出て来た予算をとってきて消化し、とりあえず活性化していると錯覚している地域も少なくないと思います。
本当は地域の中にしっかり遠くを見据えられる専門家がいることが一番望ましいのですが、そういう人がいない場合、代わってその役割を果たすことがコンサルタントの仕事でもあります。今は特に、そうした役割が求められていると思います。
再三申し上げているように、現状分析に基づく現状認識は極めて大切です。この作業が疎かになっているのでは・・・と気がかりです。先程申し上げた個人、生活者の視点から再構築・・・ということで言えば、特に観光研究を志す若者諸君には振り返って、考えていただきたいことがあります。
海外旅行が急激に伸びて来た昭和40年代後半から50年代、JTBは「衣食住・旅」というキャッチフレーズで大々的な広告・宣伝キャンペーンを展開しました。「衣食足りて礼節を知る」ではありませんが、衣食住が整ってきて、さあ旅だ、旅行だという意味もありますし、衣食住と同じように旅・旅行を生活必需品にしようという思いもこもっていると感じました。国民一人一人が一生懸命働いて、日本が豊かになって、それぞれの衣食住があるレベルに達したからこそ生まれたヒットフレーズだと思います。
翻って、現在はどうでしょうか。格差が言われ、久しかった貧困という言葉さえがしばしばマスコミに登場、特に例えば、子供の貧困のようにある特定の階層に起っていることに不安・危惧を覚えます。国民の衣食住、日常生活そのものがどうなっているのかが、改めて問われなければなりません。30年前のあの時代は、貧しかった衣食住があるレベルに達し、一億総中流の社会を前提にした旅・旅行だったわけですが、現在はどうなのか。旅行・観光活動発生の原点である衣食住そのものがおかしくなっているのではないか。観光の専門家も、専門バカと言われないように、狭い範囲の研究にとらわれるのではなく、観光で国土を、地域社会を、国民の生活を考えてみる必要があると思います。
そういう意味では、観光に携わる人達も「ギアチェンジ」が必要かもしれません。もう一度、観光を取り巻く社会状況を分析・把握しておくことが大事です。衣食住も含めた生活総体と観光との関連などを、広い視野で考える必要があると思います。特にJTBFのような旅行・観光に特化したミニミニシンクタンクでは、そういうことについて研究員同士で積極的に議論し、課題を共有することが非常に大事だと思います。
先人がこのような形で仕事をしてきたことは、もっと評価されるべきだと思うし、今、JTBFで仕事をしていることもこうしたベースの上に成り立っていることを若い人達にわかってもらいたいなと思います。それが50年の歴史、ストックというものではないでしょうか。
●専門家の目線
最後に専門家の専門性について私見を述べます。僕はしばしば「原さん!それは上から目線ですよ」と仲間や若い人達から批判されます。僕は「表現方法の問題はあるにしても、上から目線ではなくて専門家目線で申し上げている」と反論します。
専門家は例えば、“専門バカ”だとか、○○族、○○村などと揶揄されるように利益集団に迎合したり、権力に屈したりもします。観光地づくりやまちづくりの専門家の具備すべき条件は何か、改めて問われるとは思いますが、専門家もまた観光者であり、生活者・市民でもあります。専門家のこの視点が問われていると考えています。

写真4 原 重一氏への取材風景2
(2016(平成28)年11月16日、(公財)日本交通公社創発ルーム)
2013(平成25)年9月17日、2016(平成28)年11月16日、同年12月2日取材
会場:公益財団法人日本交通公社ライブラリー会議室、創発ルーム
取材者:堀木美告(現・淑徳大学)、後藤健太郎、梅川智也、通山千賀子
この研究・事業の分類
| 関連する研究・事業 | |
|---|---|
| 関連するレポート | |
| 発注者 | 公益財団法人日本交通公社 |
| 実施年度 | 2017年度 |